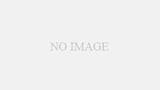「なぜ矢が上に飛んでしまうのか?」——その悩み、実は“基礎のズレ”が原因かもしれません
「どうしても矢が的の上に偏ってしまう」「しっかり引いているつもりなのに、矢が高く抜けてしまう…」。
あなたも、こんな悩みを抱えていませんか?
同じ動作をしているつもりでも、なぜ予想と違う結果になるのか――それには、射法八節の中での小さなズレが大きく影響している可能性があります。
射法八節って、ただの流れじゃない?
弓道の基本とされる射法八節には「足踏み」「胴造り」「弓構え」「打起し」「引分け」「会」「離れ」「残心」の8つの動作が含まれます。でも、本当はこれらは単なる順番ではないのです。
なぜなら、矢が上に飛んでしまう原因も、会での姿勢崩れや打起しの角度など、どこかの“節”で小さなズレが起きた結果、整体のように全体の動きに影響を与えてしまうからです。
なぜ“打起し”や“引分け”のズレが矢に影響するのか?
打起しで両腕の高さがずれたり、引分けで胸の開きが中途半端だったりすると、矢の角度が変わってしまうため、結果として矢所の偏り(とくに上方)が生じることがあります 。
たとえば:
- 打起しの角度が高すぎる → 前ではなく上に力が入って、矢が高く飛ぶ
- 会で妻手が下がってしまう → 矢先が上を向いて離れてしまう
など、一見小さな違和感でも結果には大きく影響するのです 。
「どうすればこのズレに気づけるのか?」——一人では気づきにくいズレには方法があります
自分では正しいフォームだと思っていても、実際には感覚や体の癖が影響していることもあります。動画や第三者の視点でチェックしないと、体で覚えたはずの型が本当の型になっていないということも。
それでは、どうやって筋だけでなく感覚も含めた“正しい型”を身につけるのか?
弓道射法八節習得プログラムが提供する「射法八節の本質」への気づき
そこで役立つのが、『弓道射法八節習得プログラム』。天皇杯を制しトップ選手として活躍された土佐正明先生が監修し、初心者から上級者まで「正しい動作の理解と実践」を目指せる教材です 。
特に特徴的なのは:
- 基本体型・姿勢の見直し:胴造りや五重十文字など基本を丁寧に解説
- 射法八節それぞれの動きにフォーカス:打起し、引分け、会、離れ…。各ステップを理論と映像で体感
- 中的中(中)、貫徹力(貫)、持続性(久)という3つの課題に対応する構成
この弓道射法八節習得プログラムは単なる真似ではなく、「なぜこうするのか」を学びながら、自分で実践できる内容になっているのが特徴です。
「自分にもできるのだろうか?」——初心者の不安に応える設計
初心者の方は特に、「本当に理解できるかな」「難しそう」と感じるかもしれません。でもこの弓道射法八節習得プログラムは、わかりやすい動画と解説、簡単な反復練習を通じて進められるよう設計されています。
初心者でも「まずは真似てみる」という形から始められます。
あるレビューでは、「基本体型が自然に整い、引分けから会、離れまでのつながりが手に取るように分かるようになった」「矢が安定して真っすぐ飛ぶようになった」と、感覚の定着に役立ったという声もあります 。
「本当に矢の高さが改善されるのだろうか?」——矢が上に行く悩みへの気づきと修正
「矢が上に行く」というのは、ただの失敗ではなく、自分の射のどこにズレがあるのかを教えてくれるサインでもあります。たとえば、妻手が下がっている、打起しが高すぎる、身体の重心が傾いているなど、映像を見ながら「ここがズレているのか」と気づくことが、改善への一歩です。
このプログラムでは、射法八節の全体像を理解しながら、自分の矢の軌道にも注目できる設計になっています。だからこそ、矢が上に飛ぶ悩みに対して、根本からアプローチできるのです。
まとめ:根本を見直し、小さなズレに気づくことで射は変わる
- 矢が上に飛ぶ悩みは、打起し・引分け・会など基礎のズレによることが多い
- 自分だけでは気づきにくいズレを、動画と理論の両面から補正できる
- 繰り返し学び、真似てみることで、感覚が育ち型が定着する
- 初心・中級者でも安心して取り組める工夫がある
もしあなたが、「どうしても矢が上に行ってしまう」という悩みを抱えているなら、
まずは射法八節を再確認し、小さなズレに気づくことが大切です。
そしてその第一歩として、土佐正明先生監修の『弓道射法八節習得プログラム オンライン版』は、あなたの「気づき」と「実践」を支えてくれるきっかけになるかもしれません。
一緒に、正しい型への道を歩んでみませんか?